患者UX=患者のUser Eperience(診療体験)のことです。
いまや、いろいろな業界でUXデザインというのが重要になってきています。
UXデザインとは、「使用するユーザーにとってどのようなデザインが使用しやすく、使用方法のミスなどをなくすことができるか」という観点が重要です。
病院受診のプロセスについて、病院側、行政側から求められている点は、下記の要点だと思います。
・大病院(地域医療支援病院)を受診するときには、基本的にはかかりつけ医(診療所の医師)から紹介を受けること。直接大病院にふらっとやってこないこと。
・大病院(地域医療支援病院)を受診するときには、時間内の外来を受診すること。時間外、救急外来でなくてもよい用件で救急外来を受診しないこと。準備に時間がかかった、翌日仕事で来れないからなどの理由での救急受診はしないこと。
・病院でできること、できないこと、を理解すること(症状は何もないが、何かないかが心配だから頭のMRIを取ってほしい、症状は何もないが体に異常がないか入院して全部調べてほしい、など。)
どうすれば、病院、行政側の意図した方向に患者の受診行動を促すことができるのか、というのも一つのデザイン的課題でしょう。
政策としての方法として、「選定療養費」というものが、患者側を誘導する形で機能はしています。しかし、選定療養費だけでは、あまり病院・行政側の意図がなかなか伝わらず、しかも受診後にしか機能しないという問題があります。
そもそもの住民側の医療リテラシーを上げればよいというところはありますが、それはかなりの時間とコストがかかります。
そうなると、やはり患者が受診しようとしたときに適切な受診行動を促すことができれば何よりいいのではないかと思います。
受診のパターンは、
・連絡なしで直接病院にやって来る。
・自分でホームページを見て電話をする
・家にメモしてある電話番号で電話してくる
・救急車を呼んで運ばれてくる。
どれかのことが多いのではないでしょうか。
それぞれの経路のときに、適切な受診方法を促すことができれば最適であるように思います。
しかし、受診をしたくなるような状態が差し迫っているときに、あまり患者側が悠長に余裕がないことも事実であるわけです。
簡単にできることとしては、ホームページの「受診を検討されている方へ」のページ内容の充実化、電話応対の際の窓口の対応のマニュアル化、受診した外来先での、ビデオメッセージなどを用いた適切な受診を促す啓発動画の作成
などになるのではないかと思います。
あるいは、病院受診が必要になる可能性が高い住民を、介護職などがサポートするということも重要かもしれません。
病院受診の主な対象者が高齢者になるので、それらに伝えるという点がかなり難しくなりますが、何らかの方法を用いて、病院に受診するまでのUX改善ができればよいと私は思います。

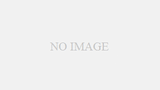
コメント